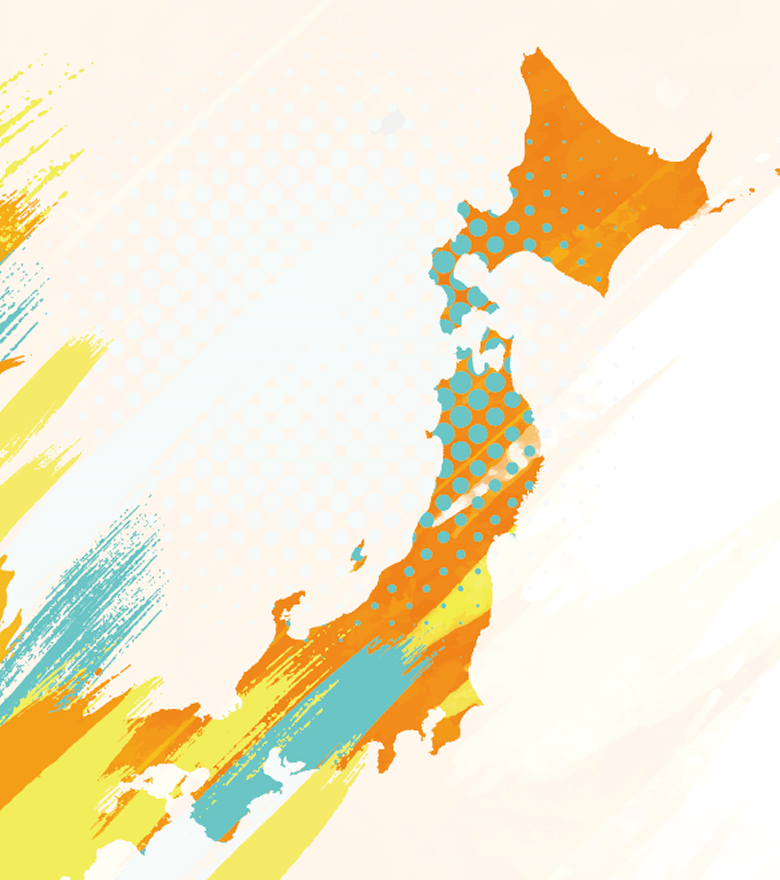――STUDIO佐賀は、佐賀県と佐賀市と、人材育成に関する協定を結んでいることでも注目されていますね。
佐賀県、佐賀市、デジタルハリウッド、そしてSTUDIO佐賀の事業母体である福博印刷との間で締結された「産業人財に関する四者協定」は、IT分野だけにとどまらず様々な方に興味関心を寄せていただいています。WEBのスキルを身につけた人材の育成は、それだけ現代の日本の中で課題になっているのかもしれませんね。
――そもそもSTUDIO佐賀の事業母体は歴史ある印刷会社ですね。紙媒体の印刷を生業とする御社が、なぜ今、デジタルハリウッドのSTUDIO事業に乗り出されたのですか?
福博印刷は佐賀県佐賀市で印刷を主軸に事業をしている会社ですが、時代の流れもあり15年ほど前からWEB事業も展開しています。自社内でWEB制作なども手がけつつひしひしと感じたのは、WEBの特性を活かし、地方でも仕事ができたり、地方でもある程度クオリティーの高い作品を制作できる環境が必要だということ。
そうした目標を持って採用活動をするのですが、志はあってもスキルが不足していたり、WEBリテラシーにギャップがあったりと、なかなか思うような人材とめぐり会えない状況が続くうちに、これは募集しているだけでなく自ら人材を育てる施策が必要なのではないかと。それも地域を巻き込んだ人材教育のしくみが必要だと。私自身はそう思うようになっていました。
人材創出は、なかなか地方の一企業が抱えきれる課題ではありませんから。デジタルハリウッドとご縁ができたのは、そういうタイミングでした。
――そうしてSTUDIO佐賀の取り組みがスタートしたのですね。
佐賀県と佐賀市のバックアップを得て、四者協定の締結が実現した――つまり自治体との接点ができ、関係性が保てるであろうということは、我が社にとって決断の決め手になったかもしれませんね。そしてSTUDIO設立から3年目になる現在は、社員や外注スタッフの中にSTUDIOの卒業生もいらっしゃるのです。
ここから自社の人材を送りこんでいるという現実も、我が社にとってはSTUDIO事業のキーポイントになっています。
――「産業人財に関する四者協定」について、もう少しお話を聞かせてください。
人材育成と、中心市街地の衰退にともなうITやクリエイティブによる集積がテーマになっています。そういう目標を掲げ、自治体と一緒に何かを一緒にやっていきましょう、と。四者協定の元、自治体の事業が立ち上がると必ずお声がけいただけるので、これは自社にとっても小さからぬメリットになっています。
また佐賀は事業誘致や企業誘致に積極的な県なのですが、佐賀に進出してもらうための理由づけとして、デジタルハリウッドのブランドと、STUDIO事業を通した人材育成に関する手厚いサポートの実績は、自治体のPRにもつながっているようです。
――デジタルハリウッドがブランド化していることを現場レベルで感じていらっしゃるということでしょうか?
非常に感じますよ。たとえば、佐賀県への進出を検討されている企業様が、STUDIOまで足を運んでくださることも少なくないのです。「本当に人材はいるのですか?」といった率直な質問をいただくこともあります。中には、本当に佐賀に「デジタルハリウッド」があるのか、その確認のためだけにいらっしゃる方も。
一方、県内の企業様の自社に対する視線が変ったことにも、デジタルハリウッドのブランドの力を感じています。「福博印刷が何だか面白いことをやっているらしい」と話題になることもあるようです。自社のイメージアップに対して、ものすごく大きな影響がありますね。
また事業そのものにとっても、これが「デジタルハリウッド」であったことの影響は大きいですね。デジタルハリウッドのブランドがあるからこそ、県外から時間をかけてでも通学する受講生があるのだとも思います。
――実際のSTUDIO運営はいかがですか? 西村さま3年目に入りある程度の認知が進んだのか、少し動き始めていることを実感しています。
スタート当時はデジタルハリウッドの存在をご存知ない方や、パソコン教室という認識で説明会にいらっしゃる方もあったのです。また私たちの運営も未熟でした。そこは時間が解決したポイントでもありますが。検討者に説明できる内容が蓄積できたり、卒業生のデータや現在の活躍を提示することもできるようになりましたから。おかげさまで受講生も増えています。
だから短期的に判断できるものではなく、ある程度のスパンで見ていかないと見えてこない事業だとは思います。実際に関わる担当者がどれだけこの教育事業を理解し、自社に対してデザインできるか、企業体の中で取り組むとしたらそうしたことも勝負のカギかもしれません。
――ご自身のキャリアを通して、STUDIO事業にはどんな意味があると思われますか?
お客様である受講生、卒業生のこれからの人生、ターニングポイントに関われる仕事です。説明会の時にHTMLもわからなかった方が、6か月後には自分の手でホームページを作れるようになっている。卒業制作発表会は本当に感慨深いものです。ある種の感動を覚えますし、それこそがこの事業の本当の目標なのかなとも思います。
すごく壮大で重たい話ではあるのですが、私自身の進むルートを変えてもらったプロジェクトだとも感じています。STUDIO事業は、ひとの気持ちに寄り添った上で教育を提供していくこと。なかなかできる経験ではありません。それを実行できているのは、会社があるからこそ。感謝しています。
――佐賀にSTUDIOを設立できて良かったと思われますか?
地域のため、社会のためにはもちろんですが、受講生ひとりひとりと触れ合ってみるとさらにそう感じますね。STUDIOは、集まって来るひとたちのそれぞれの時間が交わるところです。そういう場を提供できているのは素晴らしいことですし、そういう場がない地域よりもある地域の方が良いだろうと想像します。
――これからも、佐賀発の素敵なWEB作品やプロジェクトが生まれることを期待しています。